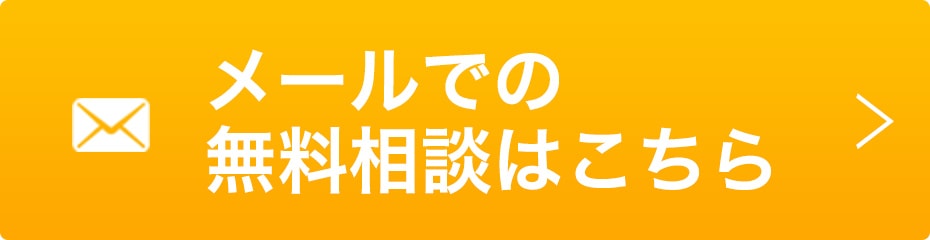労災申請の方法について知りたい方
まずは労働基準監督署に相談を
― 労災保険の請求方法について ―

労働者の方が、仕事(業務)や通勤中の事故などが原因で、負傷したり、病気になったり、死亡した場合には、労働者本人やご遺族が労災保険を請求することで、保険や支援制度による補償を受けることができます。
このページでは、主な補償の種類と請求方法について確認していきたいと思います。
なお、労災保険全体に言えることですが、提出すべき書類には記入すべき事項も多く、事業所や病院に記入してもらう部分もあることから、自分一人で提出すべき必要書類を理解し、添付書類を含めて全てを完璧に用意することは極めて困難です。
一人で悩まずに、まずは労働基準監督署の窓口に相談してみましょう。記入の仕方や、どのような添付書類を用意すればいいかなど、丁寧に教えてくれるはずです。
仕事または通勤が原因で
負傷したり病気になった場合
①療養(補償)給付

まずは労災病院や労災指定医療機関(2つを併せて「指定医療機関」と呼びます)に行きましょう。
原則として傷病が治癒(症状固定)するまで無料で治療を受けることができます。
労災保険の適用を受けるためには、「療養給付請求書」を指定医療機関経由で労働基準監督署に提出する必要がありますが、どのように記入すべきかについては、労働基準監督署や、指定医療機関、会社の総務課などに確認しましょう。
なお、指定医療機関以外で治療を受けることもできますが、その場合には、一度治療費を立て替えて、後に労働基準監督署に請求することにより、費用の全額の支給を受けることになります(療養の費用の支給)。
通院するための交通費についても、一定の要件を満たすことにより全額が支給されます。
通院交通費が全額支給されるには・・・
下記の①と②を両方満たす必要があります
①労働者の居住地又は勤務地から、原則として片道2km以上の通院であること
②同一市町村内の適切な医療機関へ通院した場合であること
労働基準監督署に提出すべき書類
指定医療機関へ通院した方
| 業務災害の場合 | 療養補償給付たる療養の給付請求書(5号) |
|---|---|
| 通勤災害の場合 | 療養給付たる療養の給付請求書(16号の3) |
指定医療機関以外へ通院した方
| 業務災害の場合 | 療養補償給付たる療養の費用請求書(7号) |
|---|---|
| 通勤災害の場合 | 療養給付たる療養の費用請求書(16号の5) |
※記入例については、「療養(補償)給付の請求手続」を参照。
②休業(補償)給付

労災の療養のために仕事を休んだことで賃金がもらえなかった場合、休業4日目から、1日につき給付基礎日額の80%(保険給付60%+特別支給金20%)の休業(補償)給付を受け取ることができます。
「給付基礎日額」とは
労働災害(労災)の直前3ヶ月分の賃金を暦日数で割ったもの(平均賃金)です。
なお、この「賃金」にはボーナスは含まず、ボーナスは別途「算定基礎日額」として把握されます。
休業(補償)給付が支払われるには、以下の要件を全て満たしている必要があります。
①業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養であること
②労働することができないこと
③賃金を受けていないこと
なお、労災保険からの支給は休業の4日目から(待機期間)であり、初日から3日目までは、業務災害の場合は事業主が1日につき平均賃金の60%の補償を行い、第三者行為による通勤災害である場合には第三者(たとえば交通事故の加害者)が補償(100%)を行うことになります。
労働基準監督署に提出すべき書類
| 業務災害の場合 | 休業補償給付支給請求書(8号) |
|---|---|
| 通勤災害の場合 | 休業給付支給請求書(16号の6) |
※記入例については、「休業(補償)給付 傷病(補償)年金の請求手続」を参照。
仕事又は通勤が原因で
親族が亡くなった場合
①遺族(補償)年金

労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父・母・兄弟姉妹は、下記の順位に従って、最先順位の者のみが年金を受け取ることができます。
労働者により生計を維持されていた必要があるため、例えば、子が労災によって死亡した60歳以上の父母であっても、父が仕事をして夫婦の生計を立てていた場合には、年金ではなく、下記の遺族(補償)一時金を受け取ることになります。
死亡診断書、戸籍の謄本等、添付書類が多岐に渡りますので、申請の際は労働基準監督署に相談しながら進めましょう。
受給権者の順位
| 1 | 妻または60歳以上または一定の障害の状態にある夫 |
|---|---|
| 2 | 18歳に達する日の年度末までの間または一定の障害の状態にある子 |
| 3 | 60歳以上または一定の障害の状態にある父母 |
| 4 | 18歳に達する日の年度末までの間または一定の障害の状態にある孫 |
| 5 | 60歳以上または一定の障害の状態にある祖父母 |
| 6 | 60歳以上、18歳に達する日の年度末までの間または一定の障害の状態にある兄弟姉妹 |
| 7 | 55歳以上60歳未満の夫 |
| 8 | 55歳以上60歳未満の父母 |
| 9 | 55歳以上60歳未満の祖父母 |
| 10 | 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹 |
※一定の障害とは、障害等級第5級以上の身体障害をいいます。
支給される額
| 遺族数 | 年金額 | 遺族特別支給金(一時金) | 遺族特別年金 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 給付基礎日額の153日分 ※ただし、その遺族が55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は、給付基礎日額の175日分 |
300万円 | 算定基礎日額の153日分 ※ただし、その遺族が55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合には、算定基礎日額の175日分 |
| 2人 | 給付基礎日額の201日分 | 算定基礎日額の201日分 | |
| 3人 | 給付基礎日額の223日分 | 算定基礎日額の223日分 | |
| 4人 | 給付基礎日額の223日分 | 算定基礎日額の223日分 |
②遺族(補償)一時金

労働者の死亡当時、遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合、給付基礎日額1000日分、遺族特別支給金300万円、算定基礎日額1000日分が、亡くなった方の遺族のうち最先順位者に支給されます。
その他、死亡した労働者の遺児などの一定の要件を満たす方に対しては、就学援護費や就労保育援護費といった援助もありますので、詳しくは労働基準監督署にお問い合わせください。
③葬祭料(葬祭給付)

遺族が葬祭を行った場合、または被災労働者の会社が社葬(恩恵的なものなどを除く)を行った場合には、葬祭の費用を負担した者に対して、葬祭料(葬祭給付)が支給されます。
葬祭料(葬祭給付)の額
31万5000円+給付基礎日額の30日分となりますが、この額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には、給付基礎日額の60日分が支給されます。
労働基準監督署に提出すべき書類
遺族(補償)年金・遺族(補償)一時金
| 業務災害の場合 | 遺族補償年金支給請求書(12号) または 遺族補償一時金支給請求書(15号) |
|---|---|
| 通勤災害の場合 | 遺族年金支給請求書(16号の8) または 遺族一時金支給請求書(16号の10) |
葬祭料(葬祭給付)
| 業務災害の場合 | 葬祭料請求書(16号) |
|---|---|
| 通勤災害の場合 | 葬祭給付請求書(16号の10) |
※記入例については、「遺族(補償)給付 葬祭料(葬祭給付)の請求手続」を参照。
既に労災保険給付を受けている場合
①傷病(補償)年金

労災によって負傷したり病気になってしまった場合、原則としては、傷病が治癒(症状固定)するまで、療養(補償)給付を受けて治療を受けることができます。
しかし、療養開始から1年6ヶ月を経過しても治癒(症状固定)していない場合には、傷病の程度(傷病等級)に応じて、下の図の額の傷病(補償)年金・傷病特別支給金・傷病特別年金を受けることができます。このとき、休業(補償)給付は傷病(補償)年金に切り替わり、支給されなくなります。
傷病(補償)年金だけは、被災者の請求に基づき支給するものではなく、労働基準監督署長の決定に基づき支給されますので、請求書等を提出する必要はありません(傷病の状態等に関する届」(様式第16号の2)を提出する必要はあります)。
支給される額
| 傷病等級 | 傷病(補償)年金 | 傷病特別支給金(一時金) | 傷病特別年金 |
|---|---|---|---|
| 第1級 | 給付基礎日額の313日分 | 114万円 | 算定基礎日額の313日分 |
| 第2級 | 給付基礎日額の277日分 | 107万円 | 算定基礎日額の277日分 |
| 第3級 | 給付基礎日額の245日分 | 100万円 | 算定基礎日額の245日分 |
②障害(補償)給付

労災保険においては、治療の結果として、完治に至らないままに傷病の状態が安定し、それ以上は良くも悪くもならない状態のことを「治癒(症状固定)」として取り扱い、その時点で後遺障害が残っている場合には、下の図のように等級に応じた障害(補償)給付が支給されます。
障害(補償)給付を請求するときは、請求書に医師の作成する診断書を添付する必要があるのが特色です。また、必要に応じてレントゲン写真等の資料の添付が必要であったり、労働基準監督署に出向いて医師との面接を受ける必要があることなどもあります。
| 傷病等級 | 傷病(補償)年金 | 傷病特別支給金(一時金) | 傷病特別年金 |
|---|---|---|---|
| 第1級 | 給付基礎日額の313日分 | 算定基礎日額の313日分 | 342万円 |
| 第2級 | 給付基礎日額の277日分 | 算定基礎日額の277日分 | 320万円 |
| 第3級 | 給付基礎日額の245日分 | 算定基礎日額の245日分 | 300万円 |
| 第4級 | 給付基礎日額の213日分 | 算定基礎日額の213日分 | 264万円 |
| 第5級 | 給付基礎日額の184日分 | 算定基礎日額の184日分 | 225万円 |
| 第6級 | 給付基礎日額の156日分 | 算定基礎日額の156日分 | 192万円 |
| 第7級 | 給付基礎日額の131日分 | 算定基礎日額の131日分 | 159万円 |
| 傷病等級 | 傷害補償一時金 | 障害特別一時金 | 障害特別支給金 |
| 第8級 | 給付基礎日額の503日分 | 算定基礎日額の503日分 | 65万円 |
| 第9級 | 給付基礎日額の391日分 | 算定基礎日額の391日分 | 50万円 |
| 第10級 | 給付基礎日額の302日分 | 算定基礎日額の302日分 | 39万円 |
| 第11級 | 給付基礎日額の223日分 | 算定基礎日額の223日分 | 29万円 |
| 第12級 | 給付基礎日額の156日分 | 算定基礎日額の156日分 | 20万円 |
| 第13級 | 給付基礎日額の101日分 | 算定基礎日額の101日分 | 14万円 |
| 第14級 | 給付基礎日額の56日分 | 算定基礎日額の56日分 | 8万円 |
また、特定の傷病については、治癒(症状固定)後においても、後遺症状の変化や後遺障害に付随する疾病の発症のおそれがあることから、健康管理手帳が交付され、保健上の措置として、定期的な診察や保健指導などを受けることができます(アフターケア)。
さらに、義肢などの補装具の購入や修理にかかった費用についても支給を受けることができ(義肢等補装具の費用の支給)、その後の義肢装着のための再手術、瘢痕の軽減などの治癒(症状固定)後の処置・診療についても自己負担なしに受けることができます(外科後処置)。これらを社会復帰促進等事業といいます。
③介護(補償)給付

重い後遺障害によって、家族や介護サービス等を受けなければならなくなった場合で下記の要件を満たすときには、介護(補償)給付として、介護に要した費用が一定の範囲で支給されます。
①障害(補償)年金または傷病(補償)年金の第1級または第2級で、高次脳機能障 害、身体性機能障害などの障害を残し、常時あるいは随時介護を要する状態にあること
②民間の有料介護サービスなどや親族、友人、知人から、現に介護を受けていること
③病院または診療所に入院していないこと
④介護老人保護施設などに入所していないこと
| 介護状態 | 傷病(補償)年金 |
|---|---|
| 常時介護 | 月額5万7110円~10万5130円 |
| 随時介護 | 月額2万8560円~5万2570円 |
まとめ
労働災害における様々な補償内容とその請求手続について確認しましたが、いかがでしたでしょうか。
冒頭でも述べたとおり、労災保険の申請手続はかなり複雑です。しかし、労災保険においては厚生労働省が詳細なリーフレットを多数用意していますので、それらも参照しつつ、自分一人で悩まずに、労働基準監督署に相談しながら進めていけば、スムーズに給付まで辿り着くことができるでしょう。