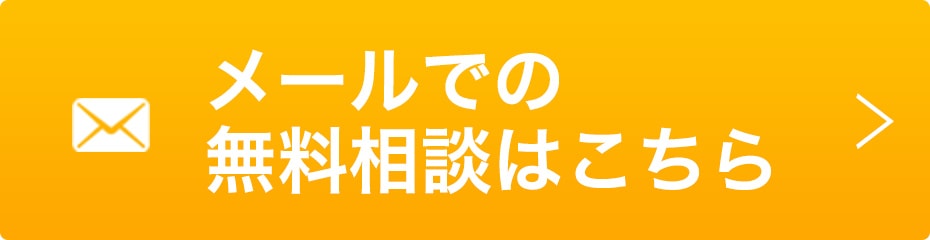休業補償について知りたい方
働くことができない場合は
休業(補償)給付を受けることが重要です
― 給付内容と手続きについて ―

業務上または通勤中の災害によりケガを負い、働くことができない場合、ケガの治療に専念するためにも、会社からの給与に代わる休業(補償)給付を受けることが重要となってきます。そこで、ケガにより仕事を休まざるを得ない場合の補償である休業(補償)給付の支給を受けるために必要な手続き等について解説していきます。
給付内容

労災の療養のために仕事を休んだことで賃金がもらえなかった場合、休業4日目から、1日につき給付基礎日額※の80%(保険給付60%+特別支給金20%)の休業(補償)給付を受け取ることができます。
※「給付基礎日額」とは、労働災害(労災)の直前3ヶ月分の賃金を暦日数で割ったもの(平均賃金)です。なお、この「賃金」にはボーナスは含まず、ボーナスは別途「算定基礎日額」として把握されます。
なお、労災保険からの支給は休業の4日目から(待機期間)であり、初日から3日目までは、業務災害の場合は事業主が1日につき平均賃金の60%の補償を行い、第三者行為による通勤災害である場合には第三者(たとえば交通事故の加害者)が補償(100%)を行うことになります。
支給要件
休業(補償)給付を受け取るためには、以下の要件を全て満たしていることが必要です。
- 業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養であること
- 労働することができないこと
- 賃金を受けていないこと
各要件について、以下に詳しく説明していきます。
①業務上の事由または通勤による負傷や傷病による療養であること

業務中や通勤中のケガが全て労災保険の補償対象となるわけではありません。
労災保険が支給されるのは、労働基準監督署(以下「労基署」といいます)により「業務災害」や「通勤災害」と認められた場合に限られます。
ご自身のケガが「業務災害」や「通勤災害」に該当するか否かについては、「労災に当たるケガ・病気について知りたい方」 をご覧ください。
②労働することができないこと

「労働することができないこと」とは、労働者が負傷しまたは疾病にかかる直前に従事していた種類の労働をすることができない場合のみではなく、一般に労働することができない場合も含むとされています。
診療担当者(医師、歯科医師、柔道整復師等)は療養のため労働することができなかったと認められる期間を請求書に記載し、その記載をもとに労基署が調査をし、この要件を満たすか否かの判断をすることになります。
なお、休業(補償)給付は、1日の所定労働時間を全て休んだ場合に限られず、たとえば通院日のように1日の所定労働時間の一部を休んだ場合にも、休んだ時間に応じて支給を受けることができます。
③賃金を受けていないこと

賃金を受けていないことというのは、全く賃金の支払いを受けていない場合に限られず、賃金の一部の支払いを受けているものの、1日あたりの支給額が1日の平均賃金の6割以下であるという場合も含みます。
まとめ
休業(補償)給付について解説をしましたが、いかがでしたでしょうか。
提出すべき書類には記入すべき事項も多く、事業所や病院に記入してもらう部分もあることから、自分一人で提出すべき必要書類を理解し、添付書類を含めて全てを完璧に用意することは極めて困難です。
一人で悩まずに、まずは労働基準監督署の窓口に相談してみましょう。記入の仕方や、どのような添付書類を用意すればいいかなど、丁寧に教えてくれるはずです。