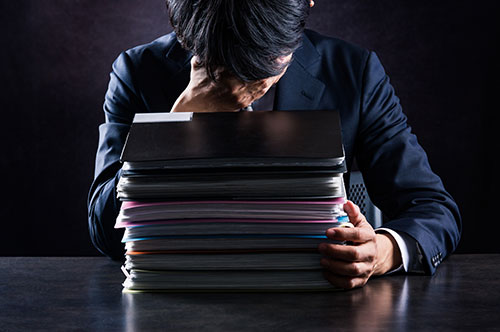
令和3年、労災が認定される基準である「過労死ライン」の見直しが行われました。改正前の過労死ラインは平成13年に定められたものであったため、約20年ぶりの改正となりました。
長時間労働などによって疲労が蓄積すると、過労死のリスクが高まります。ご家族が亡くなられた原因が過労死である可能性がある場合、遺族の方は、労働基準監督署に申請したうえで会社の損害賠償を請求することを検討すべきです。
本コラムでは、過労死が認定される基準や、家族が過労死された場合に遺族がとるべき対応について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、過労死とは
まず、「過労死」の定義や、過労死として労災が認定される際の基準について解説します。
-
(1)過労死の定義
過労死とは、長時間労働や過重労働によって引き起こされる脳・心臓疾患または精神疾患により亡くなってしまうことをいいます。
具体的には、過労死等防止対策推進法2条によって、以下のように定義されています。- 業務上の過重な負荷による脳血管・心臓疾患が原因となる死亡
- 業務上の強い心理的負荷による精神障害が原因となる自殺による死亡
- 脳血管疾患、心臓疾患、精神障害
死亡に至らない疾患についても、過労死「等」として、過労死等防止対策推進法の対象となっているのです。
-
(2)過労死と労災認定の基準
労災とは、業務が原因となって発生した負傷、疾病、死亡などのことをいいます。
したがって、過労死について労災認定を受けるためには、「過労死の原因となった疾病が、業務と関連性を有していること」が条件として求められます。
過労死の原因となった疾病が業務と関連性を有しているかについては、以下のような要素から判断されます。① 過重負荷
長時間にわたる過重労働は、疲労の蓄積を生じさせるもっとも重要な要因だと考えられています。
また、現在では、長時間にわたる過重労働と脳・心臓疾患との関連性についても、医学的な知見が得られています。
したがって、脳・心臓疾患を原因とした死亡については、長時間の残業や過大な労働時間が存在したかどうかが、業務との関連性を判断するための重要な要素となるのです。
② 心理的負荷
精神障害は、仕事によるストレスや私生活でのストレスなど、外部からのストレスによって発症すると考えられています。
そのため、仕事による強い心理的負荷が原因となって精神障害を発症した場合には、業務との関連性が認められます。
③ 異常な出来事
「異常な出来事」とは、極度の緊張、興奮、恐怖、驚愕などの強度の精神的負荷を引き起こす突発的、予測困難な異常事態や急激で著しい作業環境の変化などのことをいいます。
このような異常な出来事に遭遇した場合には、業務による明らかな過重負荷があったといえるため、業務との関連性が認められるのです。
2、長時間残業「過労死ライン」だけが基準ではない
「過労死」と聞くと、長時間残業の「過労死ライン」が基準として思い浮かぶ方が多いでしょう。
しかし、過労死認定の基準には、長時間残業といった労働時間の他の要素も存在します。
-
(1)労働時間による判断要素
厚生労働省が定めている「脳・心臓疾患の認定基準(過労死ライン)」によると、以下のような長時間労働によって脳・心臓疾患が発症した場合には、業務と過労死との関連性が強いものと評価されます。
- 発症前1か月間の残業時間が100時間を超えていること
- 発症前2か月間ないし6か月間にわたり、1か月あたりの残業時間がおおむね80時間を超えていること
-
(2)労働時間以外の判断要素
過労死ラインの認定については、上記のように労働時間も過労死と業務との関連性を判断する際の1つの要素となりますが、その他にも基準が存在します。過労死の労災認定においては、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合的に評価したうえで、判断がなされているのです。
労働時間以外の負荷要因としては、以下のものが挙げられます。
① 勤務時間の不規則性
以下のような勤務については、負荷が大きいといえるため、労働時間が短い場合でも業務と過労死との関連性が認められることがあります。- 拘束時間の長い勤務
- 休日のない連続勤務
- 勤務間インターバルが短い勤務
- 不規則な勤務、交代制勤務、深夜勤務
② 事業場外における移動を伴う業務
出張の多い業務は、通常の勤務地で働く業務に比べて労働者の心身に与える負荷が大きいため、業務との関連性が認められやすくなります。
負荷の程度については、以下のような要素をふまえて判断されます。- 出張の頻度
- 出張期間
- 交通手段
- 移動距離
- 宿泊の有無
- 出張中の休憩や休息の状況
③ 心理的負荷を伴う業務
日常的な心理的負荷を伴う業務としては、以下のものが挙げられます。- 常に自分や他人の生命、財産が脅かされる危険性を有する業務
- 危険回避責任がある業務
- 人命や人の一生を左右しかねない重大な判断や処置が求められる業務
- 極めて危険な物質を取り扱う業務
- 決められた時間どおりに遂行しなければならないような困難な業務
- 周囲の理解や支援のない状況下での困難な業務
また、心理的負荷を伴う具体的出来事としては、以下のものが挙げられます。
- (重度の)病気やけがをした
- 悲惨な事故や災害の体験、目撃をした
- 業務に関連して重大な人身事故や重大事故を起こした
- 会社の経営に影響するような重大な仕事上のミスをした
- 仕事内容の変化を生じさせる出来事があった
- 退職を強要された
- 上司からパワーハラスメントを受けた
- 職場の対人関係でトラブルがあった
- セクシュアルハラスメントを受けた
④ 身体的負荷を伴う業務
身体的負荷を伴う業務に就いている場合には、負荷の程度に応じて、業務との関連性が認められやすくなります。
負荷の程度については、作業の種類、作業強度、作業時間、作業量などの観点から検討されます。
⑤ 作業環境
職場の温度環境や騒音については、長時間の加重業務の判断にあたって、付加的な要素として評価されます。
3、脳・心臓疾患の認定基準
以下では、過労死の労災認定基準のうち、「脳・心臓疾患」を原因とする過労死認定基準について説明します。
-
(1)対象となる疾病
労災認定の対象となる脳・心臓疾患は、以下のものとされています。
- 脳内出血(脳出血)
- くも膜下出血
- 脳梗塞
- 高血圧性脳症
- 心筋梗塞
- 狭心症
- 心停止(心臓性突然死を含む)
- 重篤な心不全
- 大動脈解離
-
(2)認定基準
以下の①から③の業務に起因する明らかな過重負荷によって発症した脳・心臓疾患については、「業務に起因する疾病」として取り扱われます。
① 異常な出来事
発症直前から前日までに異常な出来事が生じたことが過労死の労災認定基準の1つとなります。
異常な出来事とは、「急激な血圧変動や血管収縮などを引き起こすことが、医学的に妥当と認められる出来事」のことをいいます。
具体的には、以下のような事態が異常な出来事と判断されるのです。- 極度の緊張、興奮、恐怖、驚愕などの強度の精神的負荷を引き起こす事態
- 急激で著しい身体的負荷を強いられる事態
- 急激で著しい作業環境の変化
② 短期間の加重業務
発症に近接した時期に、特に過重な業務に就労したことが、過労死の労災認定基準の1つとなります。
「特に過重な業務」とは、日常業務と比較して、特に過重な身体的・精神的負荷を生じさせると客観的に認められる業務のことをいいます。
また、「発症に近接した時期」とは、発症前のおおむね1週間となります。
業務の過重性が判断される際には、すでに説明したとおり、労働時間だけでなく労働時間以外の負荷要因も総合的に評価されます。
③ 長期間の加重業務
発症前の長期間にわたり、著しい疲労の蓄積をもたらすような特に過重な業務に就労したことが過労死の労災認定基準の1つとなります。
「特に過重な業務」とは、短期間の加重業務と同様に、日常業務と比較して、特に過重な身体的・精神的負荷を生じさせると客観的に認められる業務のことをいいます。
また、「発症前の長期間」とは、発症前のおおむね6か月間となります。
長時間の加重業務においても、業務の過重性を判断する際には、労働時間だけでなく労働時間以外の負荷要因も総合的に評価されます。
4、過労死が発生したとき、遺族がするべき対応
ご家族が過労死された際には、遺族の方は、以下のような対応をとりましょう。
-
(1)労働基準監督署へ申請
過労死と業務との間に関連性が認められる場合には、労働基準監督署に労災申請をして、労災認定を受けることによって、ご遺族の方に対して労災保険から各種補償が支払われることになります。
労災申請は、被災した労働者やそのご家族の負担を軽減するために、会社が手続きを行うことが一般的です。
したがって、ご家族が過労死された場合には、まずは会社の担当者に労災申請の手続きについて相談してみましょう。
会社が労災申請をしてくれないという場合には、遺族の方がご自身で労災申請をすることもできます。
手続きに不安がある場合には、労働基準監督署の窓口に相談することもできます。 -
(2)労災が認められたら会社へ損害賠償請求
労災が認定されると、過労死によって亡くなられた労働者のご遺族に、遺族(補償)年金、遺族(補償)一時金、葬祭料といった補償が支払われます。
しかし、労災保険から支払われる補償は、被災労働者やそのご家族に対する最低限の補償として位置付けられています。
そのため、過労死による損害のすべてを補償するものではないのです。
労災保険からの補償だけでは不足する部分については、会社に対して損害賠償を請求できること場合があります。ただし、労災認定を受けているからといって、必ずしも会社に対する損害賠償請求が認められるとは限りません。
会社に対して損害賠償請求をするためには、労働者の遺族の側が、会社側の落ち度(過失)や因果関係を証拠によって立証しなければならないのです。
会社側の過失を立証するためには、法律の専門的な知識が必要となります。会社への損害賠償請求を検討される場合、まずは弁護士に相談してください。
5、まとめ
会社での過重労働によって死亡した場合には、過労死として労災認定を受けることができる場合があります。また、過労死の労災認定においては、労働時間だけでなく労働時間以外の負荷要因も考慮して業務の過重性が判断されます。そのため、時間外労働が過労死ラインに達していない場合でも、労災が認定される可能性があるのです。
労災による補償だけでは十分ではない場合には、会社に対する損害賠償請求も検討する必要が生じます。しかし、会社側の過失を立証するためには法律の専門的な知識が必要となるため、個人で損害賠償を請求することは困難です。
ご家族が過労死された疑いがある場合には、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。
労災被害でお悩みの方へ
- 会社から慰謝料が
- もらえるかもしれません
- 会社から慰謝料がもらえるかもしれません
- 対象かどうかの確認だけでも構いません。
まずはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせだけでは費用は発生しません。安心してお問い合わせください。
- 初回相談料
- 60分無料
- 着手金
- 無料
- 報酬金
- 完全成功報酬
※労災保険への不服申立てを行う場合、訴訟等に移行した場合は別途着手金をいただくことがあります。
※事案の内容によっては上記以外の弁護士費用をご案内することもございます。
同じカテゴリのコラム
-

業務中の出来事が原因で労働者が怪我などを負ってしまった場合には、労災認定を受けることで労災保険からさまざまな補償が支払われます。このような労災のうち、労働者や…
-

労災保険は、労働者を対象とした保険制度ですので、役員や事業主などは労災保険に加入することはできません。しかし、一定の要件を満たす役員や事業主は、特別加入制度に…
-

業務中に機械や器具に挟まれたり巻き込まれたりして、負傷または死亡してしまうケースがあります。このような労働災害の被害にあった場合には、労災保険から補償を受けら…

